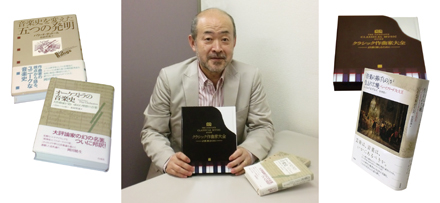
|
主な訳書に、 |
||

|
『クラシック作曲家大全』(日東書院) |
||
|
松村さんは6年ぶり2度目のご登場です。 |
|||
| ■インタビュアー:佐藤千賀子(さとう ちかこ) | |||
「クラシック音楽を“読む”と言う文化」
|
|
||
| 松村 | 前回の記事を読み返してみたら、「バッハとフリードリヒ大王の本を3つの出版社に持ち込んでボツになった」なんて話をしているんですね。まさにその本の訳書『「音楽の捧げもの」が生まれた晩』が先月、白水社から刊行されました。最初に持ち込んだ4冊の中に入っていて、そのときはひっかからなかったのですが、他の2冊を訳した段階で、編集者の方があらためて「あの本、いけるかもしれませんね」と言ってくれたんです。しかも、これは2006年頃、私が翻訳学校の生徒だった時代に初めてシノプシスを書いた本なんですね。とても厳しい先生で、もう訳文はぼろくそに言われていたのですが、このシノプシスだけは珍しくほめられました。それで調子に乗ったんですけれど。 | ||
| 佐藤 | デビュー前からの夢が叶った今も、「日本のクラシックファンに面白い本をたくさん紹介したい」という情熱は少しもお変わりになっていないようですね。 | ||
| 松村 |
今、日本でもクラシック音楽の“入門者”はたくさんいるんですね。たとえばラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポンの入場者は多いんですけど、そこから中級に進む人が少ないんです。その先は、やはり少し本を読んで、少なくともソナタ形式ぐらい理解していただかないと、次の面白さに進みにくいと思うんですよ。オペラの場合は字幕がつくようになったことがすごく大きくて、歌詞の内容を音楽で聴くという楽しみ方ができるのですが、問題は器楽……。 よく例に出すのが、チャイコフスキーのピアノ協奏曲第一番。あの有名な「タラララーラーララーラララ…」という旋律は、実は第一楽章の序奏部分に出てくるだけで、その後は二度と出てこないんです。 |
||
| 佐藤 | え、そうなんですか? | ||
| 松村 | 「そうなんですか?」ってほとんどの人が言うのですが、あの流れるような旋律は、ソナタ形式には向いていない—いわば声楽的な旋律なんです。でも、チャイコフスキーはあふれるように湧いてくる美しいメロディをピアノ協奏曲でも使いたかったのでしょう。それなら序奏にぼーんと出すことで引きつけておいて、その先は文句のつけようがないかっちりしたソナタ形式の曲を書こう、ということだったんだと思うんです。それがわかると、では、そのあとはどこが面白いのか?という話になるので、いろいろな聴き方ができるのですが、そういうことを教わる機会が、残念ながら日本ではあまりないんですね。 | ||
| 佐藤 | 欧米では、音楽教育からして違うのでしょうか。 | ||
| 松村 | アメリカの場合は、レナード・バーンスタインという超天才がいたことが大きいですね。彼は作曲家・指揮者であると同時に教育者としても稀有な存在で、実際にピアノを弾きながら「こうでしょ?」って説明したあと、実際にNYフィル指揮してばーんと音を聴かせてしまう。小学生にもマーラーやショスタコーヴィチを聴かせたり、教会旋法の話をしたりするわけです。子どもだからといって、あまり敷居を下げすぎてしまうと駄目なんですよ。そのとき理解できなくても、子どもは記憶力がよいので、あとから効いてくることもある。「ヤング・ピープルズ・コンサート」の、あのやり方に勝る教育法はないでしょうね。 | ||
| 佐藤 | たしかに、日本で子どもに聴かせようとすると、いかにも子ども向けのプログラムにしてしまう気がします。 | ||
| 松村 |
日本の場合、クラシック音楽の歴史が浅いのはしかたないのですが、あまりにも演奏家に焦点を当てすぎてしまった気がするんですね。たとえば「フルトヴェングラーが振った第九のレコードは20種類持っている」なんて人たちがいるいっぽうで、作曲家や楽曲に対する関心が意外と低い。欧米では名曲中の名曲とされているニールセンの交響曲第五番など、楽器を弾ける方でも案外知らなかったりするんです。 ベートーヴェンの交響曲第五番の「ダダダダーン」は誰でも知っているけれども、第四楽章の旋律を聴かせると「この曲、何?」という人、多いですよね。でもベートーヴェンがいなければフルトヴェングラーの第九も存在しないわけですから、もっと作曲家や曲にも興味を持ってほしい……というか、日本人にとっては、まったく違う文化の、しかも数百年も前に書かれた曲ですから、本も読まずにわかると考えるほうがおかしい……。 |
||
| 佐藤 | 音楽は好きなのに、なかなか音楽書に向かわない……というのが歯がゆいですね。ゴールデンウィークのイベント感覚でラ・フォル・ジュルネに行くような人たちが楽しく読める入門書があるとよいのですけれど。 | ||
|
松村 |
そういった意味では、チームで訳した『クラシック作曲家大全』は今までありそうでなかった本なので、目をつけられた日東書院は素晴らしいと思います。写真と絵がオールカラーですから、楽しみながら眺めていくうちに「あ、なんかこの作曲家、面白い人だな」とか、「この曲、なんか楽しそうだな」と興味を持ってもらえる。ただ、これはアングロサクソン系の人が作った本なので、イギリスとアメリカの作曲家に偏りがちなところがあるんですよね。まあ、どんな本でも編者の好みが入りますから、フランス人が書けばベルリオーズがベートーヴェンと同じくらいの扱いになるし、ドイツ人が書くとベルリオーズにはほんの数行しか触れてなかったりするので、それはしかたないでしょうね。 |
||
| 佐藤 | そういう英語の本はないんですか? | ||
| 松村 | やはり向こうは歴史が長いので、そこまで初歩的な本はあまり必要としていないのかもしれません。いっぽう日本の音楽書は二極分化で、「ウルトラマニアック」と「ひたすらCDの名演聴きくらべ」で9割占めちゃう。こうなったら、もう自分で書くか……という話なんですけど。 | ||
| 佐藤 | では、松村さんの次の目標は音楽書の執筆ですね。 | ||
| 松村 | 書くとしたら、まず「器楽の魅力は旋律ではない」ということを伝えたいんですね。「旋律を聴きたければ、オペラを聴け!!」と。それがわかると、ベートーヴェンの弦楽四重奏の面白さがわかる。バッハもそうですね。『マタイ受難曲』の『憐れみたまえ、わが神よ(Erbarme dich)』というアリアで、バッハは世にも美しい旋律をアルトに歌わせるのではなく、ヴァイオリンに弾かせているわけです。つまり、アルトの歌う旋律だけでなく、アルトとヴァイオリンのからみを聴くところに面白さがあるんです。そういうことをうまく書けたらいいなと思うんですけど、ほかに、訳したい本もまだいろいろありますし。 | ||
| 佐藤 | 今では、出版社から提案された本の翻訳やリーディングもこなしつつ、常にご自分でも原書を探していらっしゃる。うれしい課題が増える一方なのではないですか? | ||
| 松村 |
おこがましい話かもしれないですが、私の本が売れる売れない以前に、今のままだと日本のクラシック音楽市場自体が立ちゆかなくなる可能性が十分に考えられるんですね。1950〜70年代にNHKがイタリア歌劇団を呼んでオペラを上演したのですが、そのときはベルゴンツィやスコットのような人たちが日本の聴衆の反応を見て、感動していたんですね。イタリア人は上演中もおしゃべりしますけど、日本人はしーんと静かに聴いて、終わると熱狂的な拍手!! だから出演者も歌いながら感動していた。それが表情から伝わってくるんです。 でも、他にもそういう都市が増えてくると、どうなるか……今までは、東洋では日本だけが突出した市場だったかもしれませんが、世界の演奏家が「上海と北京ではやるけど、東京は行かないよ」という可能性も出てきます。なにしろ、人口が10倍と、絶対数が違いますからね。そんなことにならないために、少しでも日本のクラシックファンを増やしていかないと。 |
||
| インタビューを終えて |
| 「のだめ現象」の話をしていた2008年と今とでは、日本の経済環境も音楽市場が抱える課題もかなり違ってきています。でも、この6年間に「クラシック音楽書の翻訳家」として地歩を固めた松村さんにとっては、本当に恵みの多い変化だったと思います。いつかオリジナル本で“松村節”が聞かれる日を楽しみにしています |
| 佐藤千賀子 |
| お気軽にお問い合わせ下さい。 |

